朝起きたときから気分が落ち込んでいると、仕事や人間関係、趣味にまで影響してしまうことはありませんか?
「ご機嫌」でいることは、生まれつきの性格ではなく、実は習得できる“スキル”です。そしてこれは、アスリートだけでなく、日々成果を求められるビジネスパーソンにとっても必須の能力。
この記事では、スポーツドクター辻一郎先生の知見をベースに、「なぜご機嫌がパフォーマンスを左右するのか」「どうすればご機嫌を保てるのか」をやさしく、具体的に解説します。
読んだ後には、あなたも今日から“自分の機嫌を自分で取る”ことができるはず。
さあ、一緒に「ご機嫌マネジメント」の世界をのぞいてみましょう。
ご機嫌がパフォーマンスを決める理由
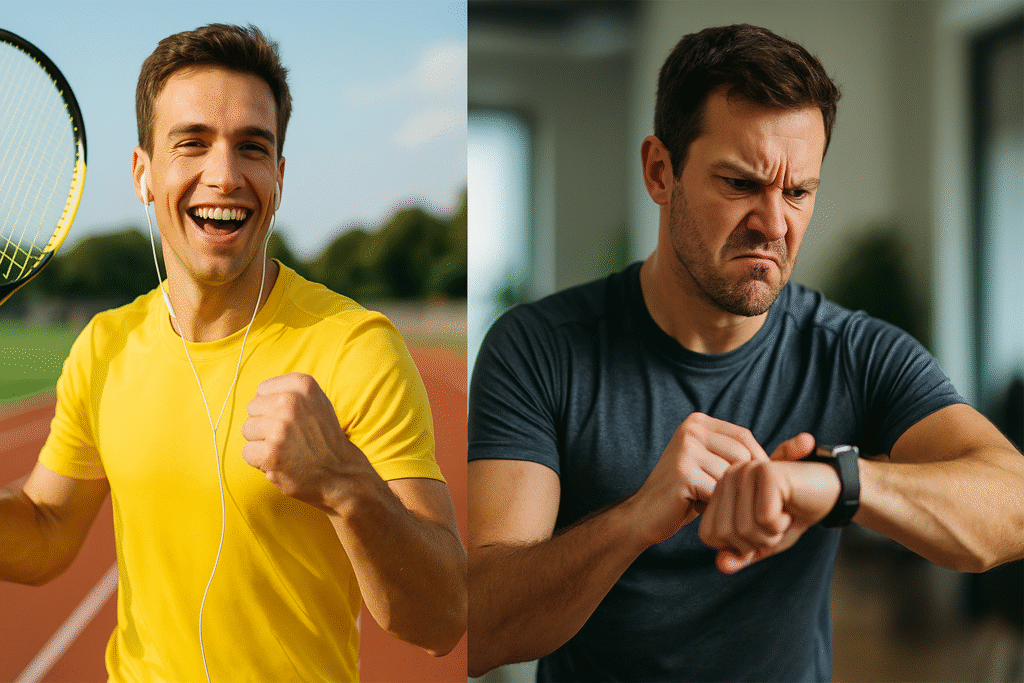
スポーツもビジネスも「心の状態」が質を左右する
スポーツの試合や大事なプレゼンの前、あなたはどんな気持ちで臨んでいますか?
ワクワクして「よし、やるぞ!」という時と、モヤモヤしてイライラしたままの時。
同じ行動をしていても、結果は驚くほど違います。
実は、パフォーマンスの“質”を決める大きな要因は「心の状態」。
アスリートが最高の記録を出す時も、ビジネスパーソンが大きな成果をあげる時も、
その背景には、落ち着きと集中力を兼ね備えた“ご機嫌な心”があります。
ポイントは「何をするか」だけでなく、「どんな気持ちでやるか」。
心が整っていると、判断力や集中力が高まり、自然と行動の精度も上がるのです。
「フロー状態」と「ゾーン」の違い
よく聞く“ゾーンに入る”という言葉。
これは、極限まで集中し、時間や周囲の感覚が消えるような究極のパフォーマンス状態です。
ただし、ゾーンは狙って入るのが難しく、持続時間も限られています。
一方で“フロー状態”は、もっと日常的に体験できる「自然体で集中できている状態」。
余計な不安や焦りに囚われず、心地よいリズムで作業やプレーが進む感覚です。
例えば、スポーツで言えばウォームアップの時から心身が軽く、
仕事で言えば会議中にアイデアが次々と湧く――そんな状態。
ご機嫌な心は、この“フロー”に入りやすくし、結果としてゾーンへの入り口にもなります。
不機嫌がもたらす悪影響とは?
逆に、不機嫌なままで行動するとどうなるでしょう。
イライラ、焦り、落ち込み…そんな感情は集中力を削ぎ、判断を鈍らせます。
- 会話の質が下がる
- アイデアが浮かびにくくなる
- 切り替えが遅くなる
- 人間関係がギクシャクする
そして一番怖いのは、その状態に自分が気づかないまま続けてしまうこと。
気合いや根性でカバーしても、質の低下は避けられません。
ご機嫌でいることは、単なる「気分の問題」ではなく、
パフォーマンスの土台を整える“必須条件”なのです。
ご機嫌をつくる4つの思考習慣

① 自分の感情に気づく
ご機嫌の第一歩は、「今の自分はどんな気持ち?」と立ち止まって確認すること。
忙しい日常では、感情よりも“やるべきこと”に意識が向きがちですが、
自分の感情に気づかないままでは、不機嫌がたまりやすくなります。
感情リストを作る練習
まずは「感情の言葉」を増やすことから。
例えば「嬉しい」「悔しい」「安心」「焦り」「ワクワク」「がっかり」…。
毎日3つ、自分の感情を書き出すだけで、
心の変化に敏感になり、ご機嫌のスイッチを見つけやすくなります。
「出来事」と「感情」の違いを理解する
「上司に褒められた」は出来事、
「嬉しい」は感情。
この違いを意識するだけで、
感情を正しく捉えられ、対処法も選びやすくなります。
② ご機嫌の価値を理解する
ご機嫌は「たまたま良い日」にだけ訪れるものではありません。
自分にとっての価値を知り、意識的に守ることができます。
不機嫌の理由よりも価値を優先する
例えば、渋滞や悪天候など、自分で変えられない不機嫌の原因に囚われるより、
「ご機嫌でいると集中力が上がる」「周りも笑顔になる」といった価値を優先。
そうすると、不機嫌に“飲み込まれない”自分でいられます。
ご機嫌を守る仲間づくり
一緒にいるだけで前向きになれる人っていますよね。
そういう人と会話し、「どうせやるなら楽しくやろう!」と声をかけ合える環境を作ると、
ご機嫌の維持がぐっとラクになります。
③ 「今ここ自分」を意識する
過去の失敗や未来の不安に心を奪われると、今のパフォーマンスは落ちてしまいます。
過去未来思考に偏らない
大事なのは「今この瞬間」に意識を戻すこと。
深呼吸をして、「今できる最善」に集中するだけでも、心は落ち着きます。
結果や他人より“今の行動”を優先する
「勝たなきゃ」「よく見られたい」よりも、
“やるべきことを丁寧にやる”ことに集中。
その積み重ねが、結果も人間関係も整えてくれます。
④ 「一生懸命の自分は楽しい」と思う
成果や評価ばかり追いかけると、楽しさは一瞬だけになってしまいます。
結果の喜びよりプロセスの喜びを増やす
目標達成の瞬間も大事ですが、
その途中で味わう「集中している自分」「工夫している自分」を楽しめると、
日常がもっと充実します。
子ども時代に戻る感覚を持つ
泥だんご作りや鬼ごっこに夢中だった頃のように、
損得抜きで一生懸命になる感覚を取り戻す。
それが、ご機嫌でいられる最大のコツです。
ご機嫌が広げる人間関係と組織の力
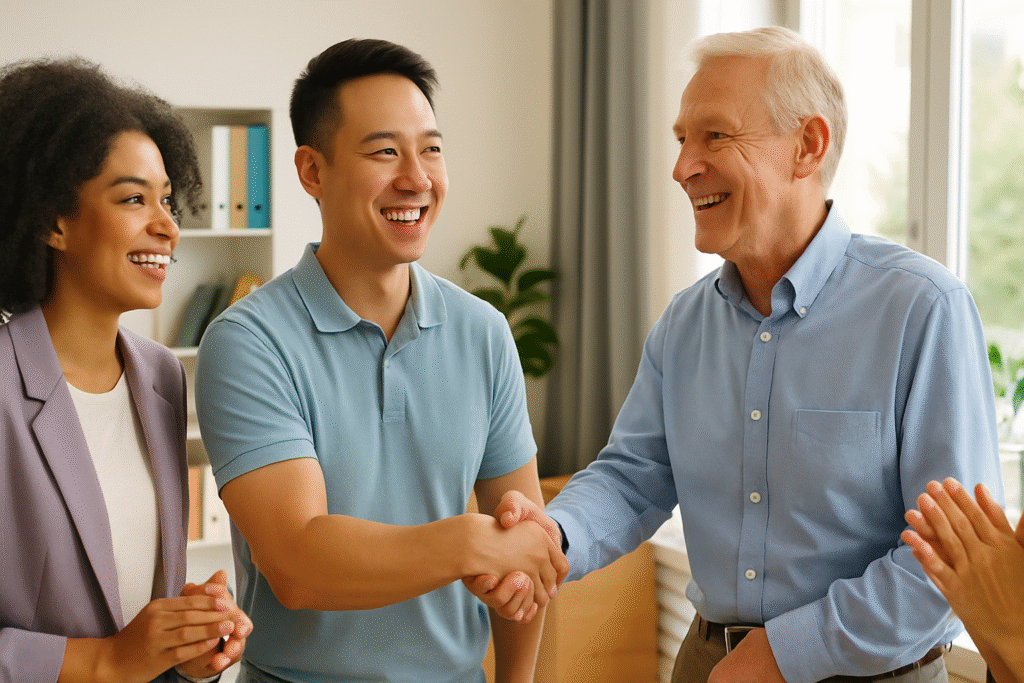
期待よりも応援を
「期待してるよ!」と言われると、一瞬うれしい反面、プレッシャーも感じませんか?
期待は、相手に“こうあってほしい”という枠をはめてしまうもの。
その枠から外れれば、期待する側もされる側も不機嫌になりやすくなります。
一方、「応援してるよ!」は、結果や方法を限定しません。
ただ純粋にエネルギーを送る言葉だから、相手は自分らしいやり方で力を発揮できます。
例えば、部下に新しい企画を任せるときも、
「期待してる」より「どんな結果でも応援するよ」と伝えるほうが、
失敗を恐れずチャレンジできる空気が生まれます。
同意より理解を
人は、感情を“わかってほしい”という強い本能を持っています。
でも私たちはつい、「それは違うよ」「私ならこうする」と“同意を求める姿勢”になりがち。
大事なのは、同意することではなく、まず「そう感じたんだね」と理解すること。
理解されると、たとえ意見が違っても安心して本音を話せるようになります。
例えば、同僚が「このプロジェクト、正直きつい」と言ったとき、
「そんなことないよ」ではなく「そう感じるくらい大変なんだね」と受け止める。
その一言が信頼関係を深め、チームの雰囲気を変えます。
結果より成長と可能性を評価する
結果は大事ですが、それだけで人を判断すると、比較やプレッシャーが増えます。
特に組織では「去年よりどうだった?」「他の部署よりどう?」といった尺度で評価されがち。
でも、結果よりも「前よりできるようになったこと」や「新しい挑戦をした姿勢」に目を向けると、
人は前向きに動き続けられます。
例えば、数字はまだ小さくても「去年より提案数が増えたね」「新しい市場に挑戦できたね」と伝える。
そんな評価は、本人の可能性を引き出し、組織全体のご機嫌度を底上げします。
ご機嫌マネジメントの実践ステップ

日常でできるトレーニング3選
ご機嫌をつくるのは特別な日だけじゃありません。
むしろ、毎日のちょっとした習慣がカギになります。
- 朝の「ご機嫌宣言」
朝起きたら、鏡の前で「今日はご機嫌でいく!」と声に出してみましょう。
不思議と一日がそのモードに引き寄せられます。 - 感情ジャーナル
寝る前に「今日の嬉しかったこと・感謝したいこと」を3つ書き出す。
書くたびに、ポジティブな出来事を探すアンテナが強化されます。 - ご機嫌スイッチを持つ
好きな音楽、香り、深呼吸など、「これをすると落ち着く」という方法を1つ決めておく。
どこでもすぐ使えるのがポイントです。
不機嫌をリセットするための合図
人間だれでも不機嫌になる瞬間はあります。
大事なのは「そのまま引きずらない」こと。
- 深呼吸を3回して肩を落とす
- 時計を見て「今ここ」と自分に言い聞かせる
- 手をグーっと握ってパッと開く(緊張をリリース)
このような“合図”を持っておくと、不機嫌の連鎖を断ち切れます。
例えば、上司からのキツい一言にモヤッとした時も、
机の下でそっと深呼吸 → 気持ちをリセット → その場での対応力アップ!が可能に。
ご機嫌を習慣化する環境づくり
人は環境に影響される生き物です。
だから、ご機嫌を習慣化するには「ご機嫌になりやすい場」を整えることが大事。
- ご機嫌な人と話す時間を増やす
会話や笑顔は伝染します。前向きな空気をくれる人を意識的に選びましょう。 - 整理されたデスク・部屋
視覚的なノイズが減ると、気持ちが落ち着きやすくなります。 - ご機嫌の“記録”を残す
写真、メモ、ボイスメモなどで「嬉しかった瞬間」を残しておくと、
落ち込みそうな時に見返して復活できます。
こうして環境と習慣をセットで整えることで、「気づけば毎日ご機嫌」が当たり前になっていきます。
まとめ
学びの振り返り
今回お伝えしたのは、「ご機嫌は生まれつきの性格ではなく、鍛えられるスキル」ということ。
そして、そのスキルはアスリートにもビジネスパーソンにも共通して必要な“パフォーマンスの土台”です。
- 心の状態が質を決める
- フロー状態に入りやすくなるコツ
- 不機嫌がもたらす悪影響
- ご機嫌をつくる4つの思考習慣
- 人間関係や組織を変えるご機嫌の力
- 日常での実践ステップ
こうして見返すと、「ご機嫌でいること」はただ気分が良いだけでなく、成果や人間関係を左右する大切な戦略だとわかりますよね。
今日からできるアクションリスト
- 朝のご機嫌宣言:「今日はご機嫌でいく!」と鏡の前でひとこと。
- 感情の言葉を増やす:毎日3つ、自分の感情を書き出す。
- ご機嫌スイッチを決める:音楽・香り・深呼吸など即効性のあるものを用意。
- 不機嫌リセット合図を持つ:深呼吸や「今ここ」と唱える習慣。
- ご機嫌な人と過ごす時間を増やす:前向きな空気を浴びる。
読者へのエール
あなたのご機嫌は、あなた自身だけでなく、周りの人の空気や成果にも波紋のように広がります。
ちょっとした工夫や習慣が、想像以上に大きな変化を生み出します。
「ご機嫌でいること」を、今日からあなたの“責任あるスキル”として育ててみませんか?
次に誰かと会う瞬間、その笑顔と心地よいエネルギーが、きっと相手の一日も明るくしてくれるはずです。
さあ、まずは深呼吸ひとつ――そして、ご機嫌モードでいきましょう!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/138e48d8.7fe5f4ea.138e48d9.b3a3f5a2/?me_id=1213310&item_id=21227792&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1119%2F9784534061119_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

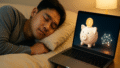

コメント